近年、ウサギを飼育する家庭が増えてきて、平均的な寿命も長くなっているなかで、体に「しこり」や「できもの」ができたという相談を受ける機会も多くなっています。
この記事では、ウサギの体表腫瘤(たいひょうしゅりゅう)について、主な種類や原因、診断方法、そして治療方針について、獣医師の視点から解説します。
Contents
体表腫瘤とは?
体表腫瘤とは、ウサギの皮膚や皮下にできる腫れやしこりのことを指します。
原因はさまざまで、大きく以下の3つに分類されます。
- 良性腫瘍:増殖はするが転移せず、生命に直接の危険を及ぼさない腫瘍
- 悪性腫瘍:周囲組織に浸潤・転移する可能性がある腫瘍 ←最も注意が必要
- 非腫瘍性病変:膿瘍や嚢胞、肉芽腫など。腫瘍ではないが腫瘤状に見える病変
腫瘤と腫瘍の違いって?わかりやすく解説します
動物の体に「できもの」ができたとき、「腫瘤(しゅりゅう)」や「腫瘍(しゅよう)」という言葉を耳にすることがありますよね。でも、この2つはどう違うのでしょうか?混同しやすいですが、実は少し意味が違います。
◆腫瘤(しゅりゅう)とは?
「腫瘤」は体の中や皮膚の表面にできる、丸く膨らんだしこりやかたまりのことを指します。良いものも悪いものも含めた“できもの”全般のことを言います。例えば、炎症でできたしこりや、脂肪のかたまりも腫瘤の一種です。
◆腫瘍(しゅよう)とは?
一方、「腫瘍」は体の細胞が異常に増えてできたかたまりのことを指します。つまり、細胞が勝手に増殖してできた「できもの」です。腫瘍は良性(体にあまり害を与えないもの)と悪性(がんなどのように悪さをするもの)に分かれます。
まとめると…
- 腫瘤は「できもの」の総称。炎症や脂肪のかたまりなども含む。
- 腫瘍は「細胞の異常増殖によるできもの」で、良性か悪性かがある。
だから、動物病院で「腫瘤がありますね」と言われても、それが必ずしも「腫瘍=がん」というわけではありません。場合によっては針を刺して細胞を採取し、そのできものが腫瘍かどうか、また良性か悪性かを判断していくこともあります。
ウサギに多い体表腫瘤の種類
腫瘍と腫瘍ではないものにわけて解説します。
腫瘍(細胞の異常増殖によるできもの)
▶ 毛芽腫(もうがしゅ)
ウサギで最も多く見られる良性腫瘍で、体幹や背中に発生します。
成長は緩やかで、手術でとることで治癒が見込めます。
▶ 線維腫・線維肉腫
線維腫は良性、線維肉腫は悪性です。
線維肉腫は周囲組織へ強く浸潤し、再発や巨大化が起こりやすいため、早期の診断と切除が重要です。
▶ メラノーマ(悪性黒色腫)
メラニンを産生する細胞由来の悪性腫瘍で、黒く見えるしこりが特徴です。
ウサギさんの顔(特に目の周りに多い)、陰嚢などに起こりやすく、やや雄に多い傾向があります。
早期に転移する傾向があり、なるべく早めの外科的切除がお勧めです。
▶ 乳腺腫瘍
ウサギの体表腫瘤のひとつとして、乳腺腫瘍も比較的よく見られます。
特に避妊していないメスのウサギに多く、良性と悪性の両方があります。多くは悪性なので注意が必要です。
外見上は他の腫瘤と区別がつきにくいです。
※より詳しい乳腺腫瘍の症状・原因・手術のタイミングなど、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓
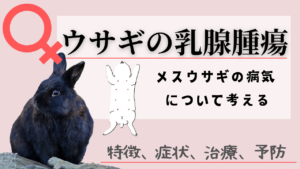
非腫瘍性
▶ 膿瘍
非腫瘍性の病変で、歯根感染や外傷などから形成されます。
皮膚の下にチーズ状の膿が溜まり、触ると硬く感じるのが特徴です。
▶ 過誤腫(かごしゅ)
腫瘍と奇形の中間的性質をもつ良性の病変でです。
特にロップイヤー種の雄に多発します。
症状
腫瘤の症状は、部位や種類によって異なります。
良性腫瘍は緩やかに成長し、痛みや出血を伴わないことが多いですが、悪性腫瘍では次のような症状が見られることがあります。
悪性腫瘍でよくみられる特徴
- 急速な腫瘤の増大
- 表面の自壊、出血、化膿
- 疼痛、元気消失
- 体重減少
- 他の臓器への転移による症状(呼吸困難、食欲不振など)
診断方法
診断には以下の方法があります。
診断について
- 手術前
- 今までの経過、視診や触診:大きくなるスピード、見た目、浸潤度合いなどであたりを付けます。
- 細胞診:細針吸引による細胞の観察を行います。正確な診断は難しいですが、ヒントになります
- 画像診断(X線、超音波、CTなど):腫瘍がすでに転移をしていないかを確認します。
- 手術後
- 病理組織検査:摘出した腫瘍の種類を特定します。確定診断ができます。
また、膿瘍との鑑別が非常に重要です。
※悪性度が高そうに見えるものについては、あらかじめの診断はせずに、早めに手術をしてしまうことも多いです
治療法
治療は腫瘤の種類や進行度に応じて選択されます。
▶ 外科的切除(手術)
良性腫瘍や転移がない悪性腫瘍では、外科的に切除することで根治が期待できます。
ただ、すでに転移が見られている場合などでは手術は適用になりません。ほかの方法を考えていく必要があります。
▶ 化学療法
ウサギにおける抗がん剤治療の有効性は十分確立されておらず、慎重に検討する必要があります。
基本的には手術でとれないものや、すでに転移が見られている子などに対して行われます。
▶放射線照射
放射線を腫瘍細胞に照射することで、腫瘍細胞の増殖を止めていくやり方です。
複数回の処置とそのたびに麻酔が必要です。実施できる施設は限られています。
▶ 温熱療法・レーザー療法
再発例や完全切除が難しい場合に用いられます。腫瘍細胞を高温で破壊する治療です。
▶ 保存療法、対症療法、緩和ケア
高齢や全身状態により手術が難しい場合、生活の質を重視した治療を行います。
腫瘍と直接は闘いませんが、うまく共存していく方法、とでも言いましょうか。
例えば腫瘍からの出血が悩ましいのであれば止血剤、腫瘍の浸潤による痛みがある場合は痛み止めを使っていくなどです。
ほかの治療とも併用できます。
ウサギの体表腫瘤を見つけたら?
腫瘍自体は痛みなどは特にないため、腫瘤がかなり大きくなるまで気づかれないこともあります。
日頃からのスキンシップで、しこりや皮膚の異常に早く気づくことが大切です。
腫瘤が見つかったら、自己判断せず、速やかにウサギに詳しい動物病院で診察を受けましょう。
早期発見・早期治療がウサギの健康と長寿を守ります。
体表以外の腫瘍についてはこちらもどうぞ↓↓
まとめ
ウサギの体表腫瘤には、さまざまな原因と治療法があります。腫瘤の正体を知るためには、適切な診断が不可欠です。ウサギの飼い主さんは、体表にしこりを見つけた際は放置せず、専門の獣医師に相談しましょう。
「しこり=がん」ではありませんが、正確な判断には病院でみてもらうことが必要です。膿瘍など腫瘍でないものも、ウサギの場合は早期治療が必要なものもあります。
何いおいても言えますが、愛するウサギの健康を守るために、日頃の観察と早めの受診を心がけましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
獣医師 たけちよ
この記事が、少しでもあなたとウサギさんの
生活に役立てば幸いです。
他にもウサギの飼い方・病気・心理などの情報をブログで発信しています。
ご質問やリクエストも大歓迎です!
SNSでも毎日、ウサギの健康や暮らしに役立つ情報を発信中!「ウサギが好き」「もっと知りたい」という方は、ぜひフォローしてのぞいてみてくださいね。

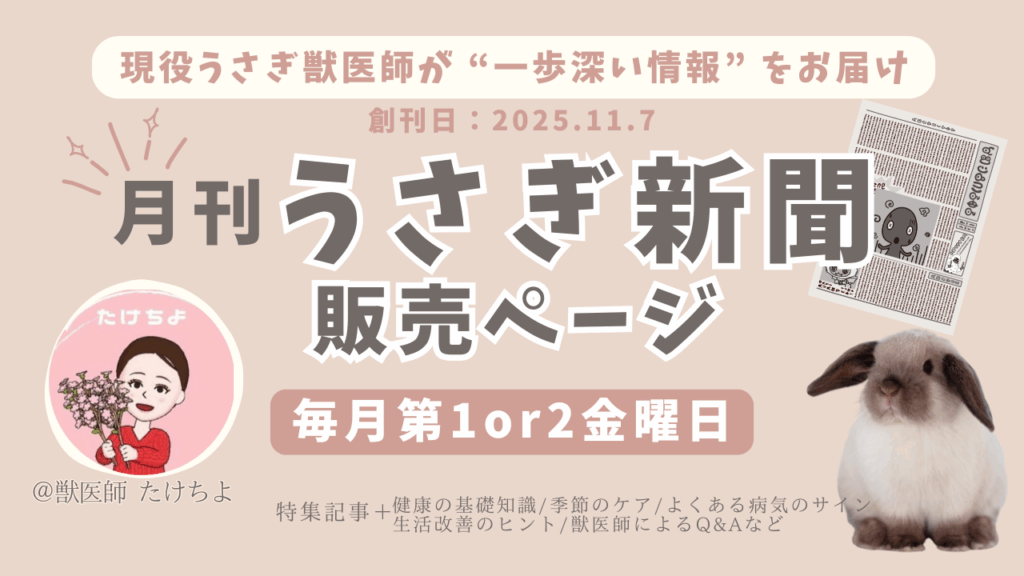


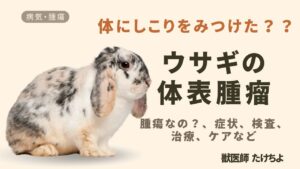

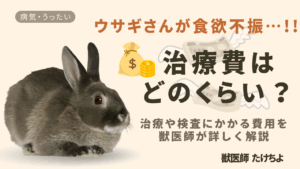
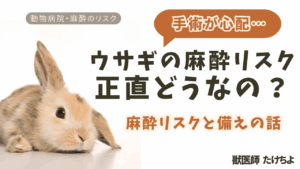




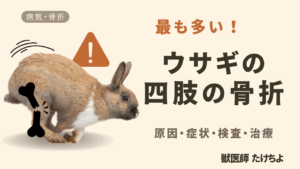
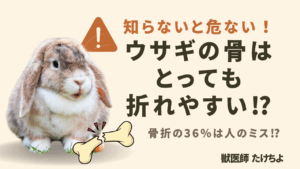
コメント